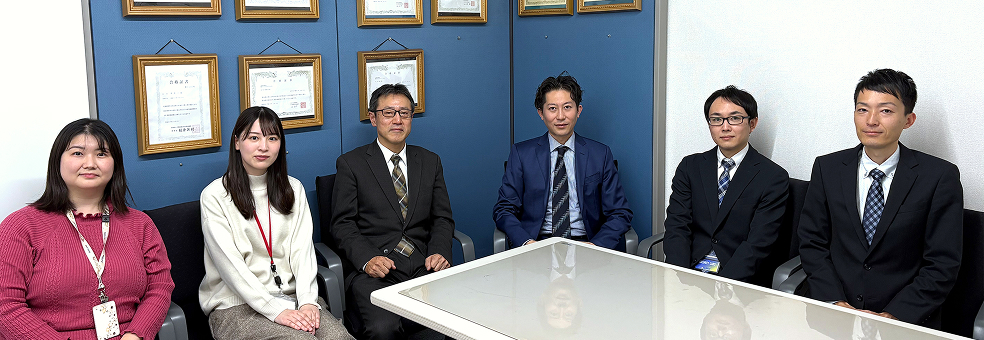
メンバー プロフィール
※名前は仮名です。
-

中堅社員
白鳥 恵
Megumi Shiratori
2013年入社
大学卒:文学部
-

若手社員
河田 真理
Mari Kawada
2024年入社
大学卒:人間科学部
-

ベテラン社員
田原 良夫
Yoshio Tahara
1988年入社
大学卒:農学部
-

中堅社員
平井 一宏
Kazuhiro Hirai
2013年入社
大学院卒:法学研究科
-

中堅社員
手塚 隆弘
Takahiro Tezuka
2014年入社
大学卒:経済学部
-

中堅社員
山本 一郎
Ichirou Yamamoto
2015年入社
大学卒:理学部
目次
自己紹介
ではまず自己紹介と前職をお伺いします。

田原
田原です。入社は1988年に営業として入社しました。前職は公務員をしていました。ダムの設計監理に携わってました。

平井
平井です。営業として2013年に入社しました。前職は会計事務所に勤めており、具体的には確定申告の作成などの仕事で、営業は当社からとなります。

白鳥
白鳥です。事務として2013年に入社しました。前職は印刷会社で営業をしていました。

手塚
手塚です。営業職として2014年に入社しました。前職は信用金庫の職員をしていました。前職では今と同じような仕事でした。

河田
河田です。事務として2023年、今年入社しました。前職は保険会社で事務をしてました。

山本
山本です。営業として2015年に入社しました。前職は害虫駆除の営業をしていました。営業なんですけど実際駆除なんかもしてました。

平井
ハチとか?シロアリとか?

山本
そうですね。あとハクビシンとかも捕まえてました(笑)
〈一同〉(笑)
社風カルチャー
さて自己紹介も済んだところで、今回はこれから当社に入社される予定の方に向けて、当社がどのような会社かより知っていただくことを目的とした座談会です。実際の会社の雰囲気や、魅力などをみなさんで話し合ってもらいたいなと思っております。
それと、30年以上勤務をしている田原さんがいるので、昔の雰囲気だったり、現在との違いなんか話して頂ければこの場も盛り上がると思いますので、まずは田原さんからお願いします。
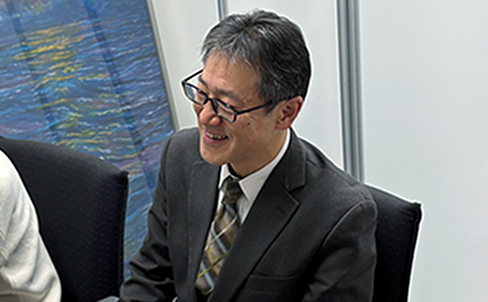

田原
そうですね。私が入社したのは昭和63年、当時は社員が100名近くいました。時代柄なのか、その当時の忙しさもあって社員の出入りは多かったイメージです。今でいう昭和気質とでも言いますか、上司も厳しく、今でこそ教育に関して懇切丁寧に教えてますが、当時は、仕事は目で盗め、という感じでした。

平井
なんか聞くところによると、その会社の中で自分が上に行くためには、知識を人たちに教えないっていうのが当たり前だったと聞きましたが。

田原
そうですね。会社としてっていうか、自分がこの会社の中で上の方に行くためには、ライバルを蹴落としてっていうような。あまり細かいところまで教育してくれないので、よく自分で本を買って勉強してましたね。

平井
昭和ですね。今では考えられませんが、時代を感じます。当社では長年勤めている方も多く、長い方だと30年、40年クラスがかなりいますよね。

河田
その方たちが長くいられている理由っていうのは、どういうところなんですか。

田原
そうですね、定時で終われるっていうのは、やっぱり1番だと思います。私が入社した時ももちろん残業は無かったので。


白鳥
1番最近入った河田さんなんかは、定時で上がれるっていう風なことを分かった上で入社したかとは思うんだけど、 実際定時で上がれているのはどんな感じ?

河田
定時になった瞬間帰るっていうのはなかったので、実際に入社して、ちょっとびっくりしました。

手塚
あんまり大きな声で言うことはできないけど、営業の方も……

山本
5時55分くらいには片付けが始まるね…
〈一同〉(笑)
社風に話しを戻しましょうか(笑)うちの雰囲気について他にはどんなこと挙げられますか?


手塚
やっぱりワンフロアのオフィスで、社員全員と顔を合わせて働くので忙しいときには仕事を手伝ってもらったりしていて仕事効率が良いと思います。

山本
自分も入社した当時、社員の方々がと仲がいいのかなっていう感じはしましたね。
仕事以外のプライベートの話とかも結構してて。

白鳥
話しやすい雰囲気があったから金融の知識がゼロでもやってこれた感は確かにあるかも。

山本
ギスギスした雰囲気がないのは本当によかったです。正直前の会社は結構ノルマがあって、週に一回の会議で上に詰められたりとかもあって……。

平井
うちは営業目標はあれどノルマはないからね。

田原
それも自分が長く続けてこられた大きな理由かもしれないな。やっぱノルマがあるとどうしても精神的に追い詰められちゃうから。

手塚
そういうのは金融業の場合、不正の原因になったりもしますからね。
河田さんなんかは入ってまだ間もなくだと思いますが、どうですか?
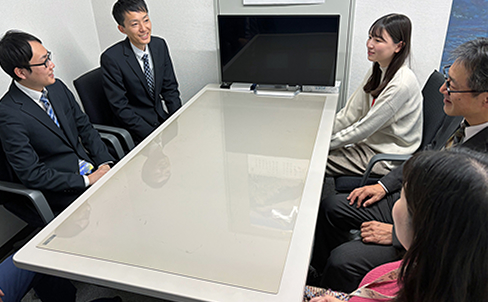

河田
前の職場は4年間勤めていたんですけど、仕事以外の話をする機会がほとんどなかったので、転職してからみなさん気さくに話しかけてくださったりとかして、すごく親しみやすい雰囲気なのかなっていうのを感じました。

白鳥
そう感じてくれているなら安心しました。

手塚
優先順位を決めて計画的に仕事をする大切さも求められるけどね。

山本
たしかに。最初はそれが結構大変。
仕事内容
仕事の話に話題が移ってきましたね。応募者の方にも一番気になる部分だと思うので、営業、事務それぞれの仕事の内容や1日の流れについて教えてください。では営業の方からお願いします。

手塚
そうですね。まず、営業としての1日の流れ、決まった流れみたいなのは多分なかなかないとは思うんですけど、大体出社した後に既存のお客様からお申し込みが来ていて、その案件を優先に審査から融資実行までを持っていきます。慣れてくれば午前中に来た申し込みを、午前中にこなせるようにもなって来ると思います。新規の申し込みがあった場合は、色々そのお客さんとやり取りをしながら必要書類をもらって、電話やメールで聞き取りをして、審査部に持っていくっていう感じです。
新人の頃は2、3日かかっていた部分もでも、やっぱり慣れてくれば1日とか割とスムーズになってくるのかなと。空き時間とかが少しできてくれば、書類整理だったりとか、基本的な顧客管理の事務作業だったりとかがあるので。最初の頃は時間がかかると思うんですけど、残業はないので、その時間内に終わらせるように優先順位をしっかり立てて仕事をしていくのが基本なのかなと。

平井
うちは優先順位を決めることが本当に大切だよね。残業がないっていうことは事実ではあるんだけど、言葉を返せば定時までにしっかり仕事を終わらせる必要があるってことだし。

白鳥
うちに残業がない理由っていうのはそもそも何でなんですかね?

平井
そうだなぁ、普通の会社っていうのは、上司が帰らないと部下は帰れないっていうのが一般的だと思うんだけど、こちらはお金という商品を扱っている以上、部下が帰らないと上司が帰れない。多分基本的な考え方がこれで、それ以外は上司が早く帰りたいからっていうのもあるのかもしれないな。
他にはどうですか?

田原
1日の流れもあるけど、月単位でみないとちょっとわからない部分がうちはある気がするな。


山本
確かにそうですね。1日中ずっと融資の審査ばっかりしてる時もあれば、そうじゃない時もありますし。
例えば1ヶ月の中で一番忙しくなるのは申し込みが増える月末。月初は比較的申し込みなどが少ない時期になりますので、前月に融資した人の書類の整理だったりとか、そういった事務作業が多かったりします。
仕事の内容や流れをもう少し具体的にお願いできますか。

田原
まず新規の場合、上長から毎朝営業担当に均等に新規申込のあったお客さんが配分されます。
その後、お客様と連絡を取り必要書類などを貰い、決裁部にもっていく稟議書を作成します。決裁で可決となれば、全国どこでもこちらからお伺いします。契約内容の説明をして、お客さんに理解して貰い、署名捺印を貰うのが一通りの流れです。ある程度営業をやっていれば、行ったことがない土地はない位にはなりますね。

平井
本当に色々な所に行きますよね。私は入社当時、毎週福岡と愛媛に出張に行っていて、そこのブロック専門みたいな言われ方もしてたな。


手塚
未だにそのイメージありますよ。私の場合、最初が東北だったから会社では東北方面に詳しい人みたいな感じになっている気がします。

山本
そんなこと言ったら私は、北海道の角の四隅ばかり行っているみたいな。。。
〈一同〉(笑)

平井
でも、みんな出張好きだよね。この間、出張規定が改訂されて結構な金額を貰えるようになったことも影響するのかもね。出張手当は年収に加算されないし、奥さんとかに内緒のヘソクリにはなるでしょ?

山本
いや、まぁ、あまり大きい声で言えませんが。。。はい。

手塚
山本さんに同じくですね笑
では次に事務の仕事内容をお願いします。

白鳥
事務の仕事はまずお客様への融資金の振込作業や入金処理、あとは各種契約書類のチェックやスキャニング、ファイリング、書類の郵送やメール送付。あとはDMの宛名リストを作成というところです。1日の流れは営業と同じく時期によって大きく変わりますね。月初は比較的ゆるやかで前月の書類処理、中旬を超えるとお客様からの入金や各種支払いが始まりますのでどんどん忙しくなる感じです。月末の申込の融資が始まるとそれに付随する業務も下旬は加わってくるので結構バタバタしているかもしれません。
教育制度
当社の業務は法律の知識や会計・不動産の知識まで多岐に渡る知識を必要とするので慣れるまで大変だと思います。仕事に慣れるまで、教育制度などは皆さんどうでしたか。

手塚
私はもともと信用金庫勤めで仕事にも近しいところがあったのでそこまで抵抗感はなかったかもしれません。それに前職の時よりもずっときめ細かく教えもらえたので、仕事を覚えていくのはむしろ前職のときより難しくなかったような気がします。あとはもう慣れていくまで何回も同じことをやっていく。例えば信用情報の集計、それに慣れると不動産の評価の仕方、という感じでOJTの先輩の横について、数をこなしました。独り立ちの時までにはその繰り返しのおかげもあり身についていましたし、慣れるのにそんなに時間もかからなかった気がします。

山本
入るまでは、やっぱすごい難しいイメージと固い印象があって不安でした。でも実際に入社すると、人はそこまで堅苦しいという感じの人はいなくて、教えてくれる人も気さくな感じで教えてくれたのでちょっとホッとしたのを覚えてますね。

平井
でも法律用語だったりとか、そういうのも覚えなきゃいけないわけだし大変だよね。何か自分の中で努力したこととかってありますか?

山本
そうですね。法律用語とかはネットとか使えばすぐ分かるときもあるんですけど、辞書に書いてあることがそのままそうなんだ、ってあっさり理解できないときもあるので難しいところでした。やっぱり実際の業務をやりながら、覚えていくことが多かったです。ずっと先輩の見様見真似をして頑張ってました。


平井
やっぱり自分がこういう営業マンになりたいなっていうことのターゲットかなんかを決めて、その人とコピーっていうかね。そういうことをすることっていうのが1番営業マンとして伸びていくポイントなのかもしれない。

山本
その時の先輩はもう40年以上勤めてる人で、お客さんからの信頼もすごく厚くて。そういう風になれればな、っていうのはすごいありました
信頼という言葉が出てきましたが、どうすればお客様に信頼されることが出来ると思いますか?

山本
やっぱりお客様の要望を極力かなえてあげることかな、と。

手塚
そうですね、ただどうしてもお客様の希望に添えない場合もあるので、そういうときはなるべく早く伝えたり、お客様に迷惑がかからないようには自分も心掛けてるかも。

田原
そうだね。断る時にはきちんとした感じで断る。無駄に引き延ばしをしないとか、 そういうようなことは大事。

平井
お客様からの信頼っていうのはどんな会社にもあることだと思うんだけど、うちの会社はもしかしたらほかの会社よりもより意識することかも。やっぱり事業資金として必ずお金って必要で、でもそれが足りなくなった時、この担当者にお願いすれば何とかしてくれる、って信頼関係を作っていくのはうちの会社ではものすごく大事だと思う。
ちょっと脱線しちゃいましたね。教育制度に話しを戻しましょう。実際どのような教育が入社してから行われるか願いします。

手塚
まず入社してからは、一週間ぐらいの間に、基本的には座学研修みたいな形で、業界の専門用語に関してや、お客様の業界の基本的な知識だったり、そういったものをまず勉強していきます。その後、その座学研修が終わると、もう基本的には各教育担当者の方の下でOJTっていう形で、実践形式の勉強になっていきます。本当にマンツーマンでついてくれるので、例えばその方が外勤に出る時とかは一緒に同行して、実際の契約はどういうものなのかとか、お客さんと話している営業トークなど、そういった部分をすぐ近くで見ることができるので、いいのかなと思います。

平井
しっかり契約の説明や、基本的なことがちゃんとできるようになったらお客さんが振り分けられて独り立ちだね。そこまでいくのに、人によってちょっと違うけど、大体半年から8か月くらいかな。
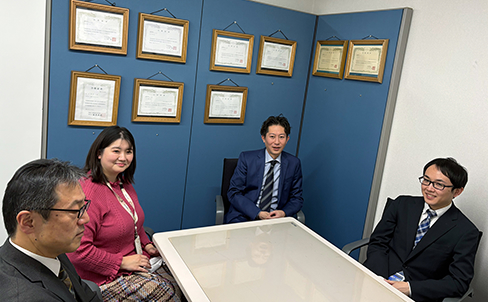

手塚
あと営業の方には貸金業務取扱主任者の資格を取らなければならないので、実務と一緒に資格勉強もしなければならないですね。

白鳥
たしかこれがまた難しいんですよね。たしか合格30%くらいだったような。

山本
うん。貸金業法の他に民法とかも範囲だから覚えること多いし…実際1回落ちたし。

手塚
私も1度落ちました。1年目でその貸金業務取扱主任者の勉強した時は、やっぱり法律用語とかが多くて、なかなか頭に入ってこなかった。ただ、翌年受かった際には、1年間一応うちで実務をこなしているので、実務でやっている内容が勉強というか、そっちにもリンクしてきて、点と点だったのが、それが繋がって線になってみたいな感じでわかるようになったかな。

平井
1回目と2回目でやっぱ全然違った?

手塚
全然違いました。1回目は正直自信なかったんですけど、2回目は多分大丈夫じゃないかなって合格発表を待てたので。

平井
まぁ、君たち以外はみんな1回で受かっているよ笑
田原さんも私も「一番難しいと言われた(嘘)」第1回貸金業務取扱主任者の試験に合格してるからね笑
他には入社して3ヶ月位で合格した人もいたし。

田原
うちの会社の当時の営業部隊は全員第1回目の国家試験で一発合格してますからね。
では事務の方の教育制度に話しを移したいと思います。最近入社した河田さんどうですか。

河田
事務は入社して2日間ほど座学で会社の概要だったり専門的な用語について教えていただいて、その後はもう営業さんと同じ感じで、OJTの教育担当の方に業務を教えていただきました。今は融資金の振り込みの手続きなどもしています。

白鳥
ちょっと話は戻っちゃうかもしれないですけど、業界用語だったりとか、法律用語だったりとか、そういうものが会社の中で色々飛び交ってるかと思うんだけど、そういうのには慣れてきました?

河田
まだちょっと難しいなって感じます。でも最初に比べたらなんとなくわかるようになってきたかもしれないです。実務をすることによってなんとなくっていう感じですね。
福利厚生
さて営業の方で貸金業務取扱主任者の試験の話しがでてきたところで、当社の福利厚生の方に話しを移していきたいと思います。

白鳥
たしか主任者試験は試験代出るんですよね?

山本
テキスト代もね。

田原
意外と過去問の本とか高いからね。

平井
他に、当社の福利厚生の利用は白鳥さんが今、時短勤務だったね。

白鳥
はい。産休育休の復帰後から時短にさせていただいてます。うちの会社は始業時間か終業時間のどちらか調整するのを選べるんですけど、私は終業時間を1時間早くしてもらって今は16時に帰ってます。みんな快く送り出してくださるのでほんとありがたいです。

田原
他は出張手当とか?

山本
それで出張先でご当地の美味しいもの食べてる人とか結構いますね。


白鳥
結構出るんですか?うなぎ食べられるくらい出ます?

田原
うなぎは食べられるよ(笑)
〈一同〉(笑)
面接の雰囲気、流れ
次はそうですね、応募者さんにとって気になることと言えば選考ついてだと思うのですが、面接の雰囲気などについて、皆さんどうでしたか?

手塚
10年以上前で正直あんまり覚えてない……(笑)

白鳥
私たちの世代は面接も1回だけだったりするから今とは少し違うかもね。ここは一番最近に試験を受けた河田さんに聞くのがいいでしょうね。どうでした?

河田
面接は私すごく緊張してしまう方なので、当日も緊張しながら行ったんですけど、もうすごく目を見ながら話を聞いてくださったりとかして、話しやすい雰囲気で進めることができました。一次面接は白鳥さんが面接官だったので、実際に事務をされてる方のお話とかも聞いて、働くイメージもつきやすかったなと思います。

平井
二次面接はどうだった?


河田
二次面接は、なんか面接っていうよりもちょっと雑談みたいな感じで、一次面接の時よりも、和やかに話せたかなと思います。

白鳥
面接終わった後、受かった手ごたえとかあった?

河田
いえ、なかったです。一次面接のときのテストが全然出来た気がしなかったので。

平井
まあ、筆記テストはあくまで基礎知識を見るものであって、一番は人間性を見てます。試験結果はすべてじゃないので、これから受ける応募者の方も安心して受けてもらいたいですね(笑)
求める人物像
さてここまでいろいろと話してきましたが、最後に当社に向いている人ってどんな人だと思いますか?

田原
まずワークライフバランスがとりたいと思っている人には向いていると思う。

白鳥
たしかに、残業いっぱいして残業代を稼ぎたい、という人にはうちはあんまり向いていないかもしれないですね。

田原
ノルマがあるとやっぱり体力的にも精神的にも、結構きついと思うんだよね。年を取れば体もガタがくる時も出てくるわけだし、長い目で見ると、うちで長く勤めていける安定感っていうのは非常に魅力的だと思う。
ほかにはどうですか?
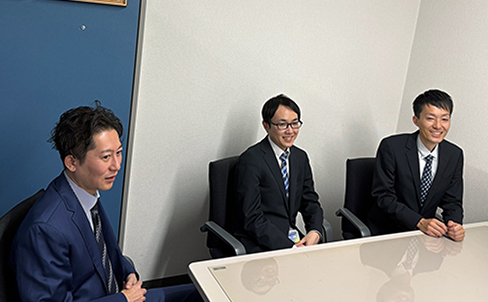

手塚
あとはもともと法律になじみがある法学部出身とかだと有利かなと。

山本
知識欲が高い人に向いていると思います。何年やっても日々勉強の部分があるので。

平井
知識欲が高いっていうのは本当にそうだと思う。お客さんのことを思えば、入れなきゃいけない知識っていうのがたくさん出てくると思うんだよね。お客さんのために勉強できる、つまりサービスの質を上げることを考えられるかという部分。

田原
そうですね。うちの営業は、営業とは言ってもなんですかね、事務的な書類作成もあるけど、法律的な部分では学ぶことが多いので、さっきみたいにその残業代で稼ぐだとか、自分の足使ってなんかいっぱい仕事取ってきて稼ぐだとか、そういった営業よりは、色々な知識を身につけて行きたい人、そういう人の方が向いているんじゃないかなっていうのはあります。

平井
あと一番の大切なことっていうのは、これはどの仕事にも共通することだと思うんだけど、継続できる力を持っているかどうかってことかな。仕事としては審査して融資するということの繰り返しだけど、お客さんは一人一人に感謝して貰えることが実感出来ればやりがいに繋がると思うんだよね。そのためにも、基礎能力の下地があれば、難題に直面しても解決する能力が付き、どんどん仕事が面白くなっていくもの。だから常に新しい知識をアップデートし続ける方っていうのがやっぱり向いている方なのかなと。逆にそれができない方は向かないのかなと思いますね。
長い時間、ありがとうございました!
株式会社トミンシンパンは2025年12月をもって創立60周年を迎えます。
昭和、平成、令和の三世代、困難に直面することもありましたが、何度も困難を乗り越えて現在に至ります。
次の100年、さらにその先まで続く企業を目指し、共に歩んで頂ける方を募集しています。
本座談会により弊社のことをより知って頂けたのであれば幸甚です。
詳細ページ
